元本はそのままに配当だけ頂くという「じぶん年金」の主力商品を国内S&P500ETFの2558にしています。
海外ETFならVYM一択で良かったのですが、国内ETFだと選択肢が一気に減りますね。
とはいえ、2558は信託報酬も安く実質コストも0.15~0.17%くらいと考えると悪い商品ではありません。
なにより二重課税調整を自動でしてくれるのが大きなメリット。
勢いで投資をしてから考えるのも良いのですが、せっかく調べたので記事にてシェアできればとも思っていました。
海外ETFはちょっと…という方の参考になれば幸いです。
S&P500ETF、SPYの長期配当推移と増配率を調べてみた

おさらい|米国株と二重課税について
まずはおさらいとなりますが、二重課税についてご紹介。
米国株投資をしていると配当に対してアメリカで10%が引かれ、国内でも配当課税として20.315%が引かれます。
実質手取りは70%近くに減ってしまう計算になりますね。こうなると高配当ETFなのに国内ETFとあまり変わらないということも。。
例えばVYMに比べると2558の受け取る配当金は小さいのですが、実質手取りはかなり近づきます。
| 銘柄 | 2558 | VYM |
| 配当利回り | 1.53%※ | 3.19% |
| 実質手取り | 1.22% | 2.29% |
| 為替 | 円建 | ドル建て |
| 信託報酬 | 0.085% | 0.06% |
| 運用会社 | 三菱UFJ国際投信 | バンガード |
高配当ETFのVYMとはいえ、手取りで見ると悲しくなりますね。S&P500は配当が低くなるものの、二重課税調整後は1%の差。
今はバリュー優位なので、去年くらいまでは1%未満でした。
高配当ETFが市場平均より劣ってきた事実を考えると
- S&P500で1.2%の配当手取り
- VYMで2.2%の配当手取り
だと、S&P500ETFでもええかな、と。
というか、ずっと悩みそうなテーマではありますが。
というワケで、S&P500の配当推移って実際どうなの?と思ったので調べました。Yahoo!financeから手作業で。
(どこか配当実績が一発で見られるサイト知ってたら教えてください。。)
最古のS&P500ETFであるSPYから調べた配当金推移
結論部分からサクサクと出していきます。

SPY(S&P500ETF)の株価&配当金推移
左:SPY株価(オレンジ) 右:配当金(青)
最古のETFだけあって1993年から調べられるのが良いですね。
円安で実感なかったものの、オレンジの株価を見ると下落幅が凄いことに。。
1990年から2000年序盤までは思ったほど配当が増えていなくて意外でした。こういったのは調べてみると参考になりますね。
少ない時は1%近くになる
現時点で2%程度
と思っておくと良いかな、と思います。
画像を見て分かるのは
S&P500指数が上がると配当金も増える
という単純ですが強力な事実ですね。
これは超長期で保有するときは心強く感じます。
せっかくなので調べたものをテキストでずらーっと見てみましょう。長いので雑に読み飛ばして下さいw
配当利回りは年4回配当なので、4倍にすると良い感じです。
| 月日 | 配当金 | SPY株価 | 配当利回り |
| 1993/3/21 | 0.21 | 44.3 | 0.48% |
| 1993/6/18 | 0.32 | 45.3 | 0.70% |
| 1993/9/17 | 0.29 | 46.4 | 0.62% |
| 1993/12/17 | 0.32 | 46.5 | 0.68% |
| 1994/3/18 | 0.27 | 45.9 | 0.59% |
| 1994/6/17 | 0.31 | 45.9 | 0.66% |
| 1994/9/16 | 0.29 | 46.4 | 0.62% |
| 1994/12/16 | 0.36 | 45.0 | 0.81% |
| 1995/3/17 | 0.27 | 48.5 | 0.55% |
| 1995/6/16 | 0.32 | 53.1 | 0.60% |
| 1995/9/15 | 0.31 | 58.3 | 0.54% |
| 1995/12/15 | 0.38 | 60.3 | 0.63% |
| 1996/3/15 | 0.29 | 64.9 | 0.44% |
| 1996/6/21 | 0.35 | 67.2 | 0.52% |
| 1996/9/20 | 0.35 | 70.3 | 0.50% |
| 1996/12/20 | 0.37 | 73.3 | 0.50% |
| 1997/3/21 | 0.30 | 77.0 | 0.39% |
| 1997/6/20 | 0.35 | 85.2 | 0.41% |
| 1997/9/19 | 0.35 | 93.1 | 0.37% |
| 1997/12/19 | 0.38 | 96.8 | 0.39% |
| 1998/3/20 | 0.31 | 105.1 | 0.30% |
| 1998/6/19 | 0.35 | 112.0 | 0.31% |
| 1998/9/18 | 0.36 | 101.7 | 0.35% |
| 1998/12/18 | 0.39 | 119.5 | 0.33% |
| 1999/3/19 | 0.32 | 124.3 | 0.26% |
| 1999/6/18 | 0.41 | 134.3 | 0.30% |
| 1999/9/17 | 0.37 | 127.8 | 0.29% |
| 1999/12/17 | 0.35 | 141.4 | 0.25% |
| 2000/3/17 | 0.37 | 151.4 | 0.24% |
| 2000/6/16 | 0.35 | 138.0 | 0.25% |
| 2000/9/15 | 0.38 | 151.3 | 0.25% |
| 2000/12/15 | 0.41 | 131.2 | 0.31% |
| 2001/3/16 | 0.32 | 123.6 | 0.26% |
| 2001/6/15 | 0.35 | 126.7 | 0.27% |
| 2001/9/21 | 0.37 | 104.4 | 0.35% |
| 2001/12/21 | 0.39 | 114.1 | 0.34% |
| 2002/3/15 | 0.33 | 117.0 | 0.28% |
| 2002/6/21 | 0.35 | 107.2 | 0.33% |
| 2002/9/20 | 0.38 | 89.7 | 0.42% |
| 2002/12/20 | 0.44 | 89.3 | 0.49% |
| 2003/3/21 | 0.35 | 84.1 | 0.42% |
| 2003/6/20 | 0.36 | 99.6 | 0.36% |
| 2003/9/19 | 0.40 | 102.5 | 0.39% |
| 2003/12/19 | 0.52 | 108.1 | 0.48% |
| 2004/3/19 | 0.40 | 112.6 | 0.35% |
| 2004/6/18 | 0.41 | 114.4 | 0.36% |
| 2004/9/17 | 0.47 | 113.2 | 0.41% |
| 2004/11/15 | 0.35 | 117.3 | 0.30% |
| 2004/12/15 | 0.57 | 119.4 | 0.48% |
| 2005/3/18 | 0.47 | 120.4 | 0.39% |
| 2005/6/17 | 0.49 | 120.2 | 0.41% |
| 2005/9/16 | 0.52 | 124.6 | 0.42% |
| 2005/12/16 | 0.67 | 126.4 | 0.53% |
| 2006/3/17 | 0.52 | 128.6 | 0.40% |
| 2006/6/16 | 0.56 | 124.7 | 0.45% |
| 2006/9/15 | 0.58 | 131.4 | 0.44% |
| 2006/12/15 | 0.79 | 140.8 | 0.56% |
| 2007/3/16 | 0.55 | 138.7 | 0.40% |
| 2007/6/15 | 0.66 | 153.1 | 0.43% |
| 2007/9/21 | 0.72 | 148.9 | 0.48% |
| 2007/12/21 | 0.78 | 147.2 | 0.53% |
| 2008/3/20 | 0.64 | 132.1 | 0.49% |
| 2008/6/20 | 0.67 | 127.5 | 0.52% |
| 2008/9/19 | 0.69 | 124.1 | 0.56% |
| 2008/12/19 | 0.72 | 89.0 | 0.81% |
| 2009/3/20 | 0.56 | 76.1 | 0.74% |
| 2009/6/19 | 0.52 | 94.6 | 0.55% |
| 2009/9/18 | 0.51 | 106.7 | 0.48% |
| 2009/12/18 | 0.59 | 111.1 | 0.53% |
| 2010/3/19 | 0.48 | 115.5 | 0.42% |
| 2010/6/18 | 0.53 | 109.7 | 0.48% |
| 2010/9/17 | 0.60 | 112.5 | 0.54% |
| 2010/12/17 | 0.65 | 124.3 | 0.53% |
| 2011/3/18 | 0.55 | 127.8 | 0.43% |
| 2011/6/17 | 0.63 | 127.1 | 0.49% |
| 2011/9/16 | 0.63 | 113.5 | 0.55% |
| 2011/12/16 | 0.77 | 126.4 | 0.61% |
| 2012/3/16 | 0.61 | 140.3 | 0.44% |
| 2012/6/15 | 0.69 | 133.5 | 0.52% |
| 2012/9/21 | 0.78 | 145.9 | 0.53% |
| 2012/12/21 | 1.02 | 142.8 | 0.72% |
| 2013/3/15 | 0.69 | 155.8 | 0.45% |
| 2013/6/21 | 0.84 | 163.2 | 0.51% |
| 2013/9/20 | 0.84 | 169.3 | 0.49% |
| 2013/12/20 | 0.98 | 178.1 | 0.55% |
| 2014/3/21 | 0.83 | 184.7 | 0.45% |
| 2014/6/20 | 0.94 | 195.9 | 0.48% |
| 2014/9/19 | 0.94 | 200.7 | 0.47% |
| 2014/12/19 | 1.14 | 200.9 | 0.56% |
| 2015/3/20 | 0.93 | 205.8 | 0.45% |
| 2015/6/19 | 1.03 | 210.0 | 0.49% |
| 2015/9/18 | 1.03 | 196.7 | 0.53% |
| 2015/12/18 | 1.21 | 200.0 | 0.61% |
| 2016/3/18 | 1.05 | 202.8 | 0.52% |
| 2016/6/17 | 1.08 | 210.1 | 0.51% |
| 2016/9/16 | 1.08 | 213.4 | 0.51% |
| 2016/12/16 | 1.33 | 226.5 | 0.59% |
| 2017/3/17 | 1.03 | 237.0 | 0.44% |
| 2017/6/16 | 1.18 | 243.4 | 0.49% |
| 2017/9/15 | 1.24 | 246.6 | 0.50% |
| 2017/12/15 | 1.35 | 257.9 | 0.52% |
| 2018/3/16 | 1.10 | 258.1 | 0.43% |
| 2018/6/15 | 1.25 | 277.1 | 0.45% |
| 2018/9/21 | 1.32 | 285.1 | 0.46% |
| 2018/12/21 | 1.44 | 260.5 | 0.55% |
| 2019/3/15 | 1.23 | 279.3 | 0.44% |
| 2019/6/21 | 1.43 | 293.0 | 0.49% |
| 2019/9/20 | 1.38 | 298.3 | 0.46% |
| 2019/12/20 | 1.57 | 311.0 | 0.50% |
| 2020/3/20 | 1.41 | 269.3 | 0.52% |
| 2020/6/19 | 1.37 | 308.6 | 0.44% |
| 2020/9/18 | 1.34 | 330.7 | 0.40% |
| 2020/12/18 | 1.58 | 369.2 | 0.43% |
| 2021/3/19 | 1.27 | 389.4 | 0.33% |
| 2021/6/18 | 1.37 | 414.9 | 0.33% |
| 2021/9/13 | 1.42 | 441.4 | 0.32% |
| 2021/12/17 | 1.63 | 459.8 | 0.35% |
| 2022/3/18 | 1.36 | 444.5 | 0.31% |
| 2022/6/17 | 1.57 | 365.8 | 0.43% |
では年間の配当利回りと増配率という点でも見ていきましょう。
こちらもけっこう意外に感じました。
S&P500ETF(SPY)の配当利回りと増配率推移

左:配当利回り(青)右:増配率(オレンジ)
25年以上のデータになるので、そこそこ将来の参考になるかな、と。
配当利回りは株価によってブレますが1.5~2.0%の間を見ておけば大きく外さないでしょう。
1%付近に近付いたときは株価暴騰中なので資産全体としては大きくプラスなはず。もうウハウハ状態。(今は良いタイミングなのかも。)
逆に2.5%を超えたときは注意が必要で、その後に暴落→受難の時代を迎えます。
配当利回りは想像通りそこまで高くありませんでした。
一方で驚いたのは増配率ですね。詳しく見てみましょう。
意外とS&P500ETF(SPY)の増配率は高い
もう一度画像を見て頂きたいのですが、意外と増配率は悪く無いのです。

配当利回りのように増配率も2%くらいかと思っていたら、平均すると6%でビックリしました。
もちろんITバブル崩壊とリーマンショックで大きく下がっていますが、リバウンドもしっかりあるので長い目で見れば増配率は思ったより高そうです。
同じようにせっかく調べたのでテキストでも見てみましょう。今度は配当利回りを年に落としています。
| 月日 | 配当利回り | 増配率 |
| 1993年 | 2.44% | 0% |
| 1994年 | 2.72% | 8.2% |
| 1995年 | 2.19% | 4.2% |
| 1996年 | 1.85% | 6.0% |
| 1997年 | 1.42% | 1.6% |
| 1998年 | 1.18% | 2.8% |
| 1999年 | 1.02% | 2.0% |
| 2000年 | 1.15% | 4.2% |
| 2001年 | 1.25% | -5.4% |
| 2002年 | 1.68% | 5.2% |
| 2003年 | 1.51% | 8.8% |
| 2004年 | 1.84% | 34.8% |
| 2005年 | 1.70% | -2.2% |
| 2006年 | 1.74% | 13.8% |
| 2007年 | 1.84% | 10.4% |
| 2008年 | 3.06% | 0.7% |
| 2009年 | 1.96% | -20.0% |
| 2010年 | 1.82% | 4.1% |
| 2011年 | 2.04% | 13.7% |
| 2012年 | 2.17% | 20.5% |
| 2013年 | 1.88% | 8.0% |
| 2014年 | 1.91% | 14.5% |
| 2015年 | 2.10% | 9.6% |
| 2016年 | 2.00% | 7.9% |
| 2017年 | 1.86% | 5.8% |
| 2018年 | 1.96% | 6.2% |
| 2019年 | 1.81% | 10.2% |
| 2020年 | 1.54% | 1.0% |
| 2021年 | 1.23% | 0% |
数字で見ると増配率がエグいですね。また配当利回りとあまり関係ないようにも思えます。
2010年以降は、指数の伸びが異次元レベルだったので後半は無理やり押し上げられた、に近いかも。
しかしリーマンショック前の米国株暗黒時代(マジで暗黒時代だったんですよ…)でも、配当の伸びについては文句の付けようがないですね。
マジで指数が成長しなくても24年くらい放置していれば配当が4倍というのは現実的ラインなのかも。
また、こういった数字を見ていると
配当は下落相場のプロテクター、上昇相場のアクセル
と株式投資の未来のシーゲル教授の言葉を思い出します。
個人的にはS&P500の配当でも十分に満足して投資を続けられるように感じました。
コロナショック以降、上がり過ぎた株価の調整が来ましたが減配までは来ていません。2021年は前年度と同額で増配0%でした。
というワケで、VYMとBNDは引き続き配当金などで購入をしつつ、2558を使った「じぶん年金」作りもしていこうと思います。
まとめ|S&P500ETF、SPYの長期配当推移と増配率は長期投資にも効果絶大

S&P500というと、最近のグロース優位から配当が低いという思い込みがありましたが、意外と増配率は高く、むしろ長期保有をして元本に対して20年後の実質利回りを見たほうが幸せではないか?と思うようになりました。
配当利回りはざっくり1.5%くらい。
増配率はざっくりですが6%くらい。
配当金は約12年で2倍、24年で4倍になるペースです。ということは、現在100万円投資をして1.5%の配当=年1.5万円の配当だとすると24年後には年6万円ですね。
1000万円だと年60万円。これは夢があります。
値動きは想像以上ですが、超長期で配当を生み出すキャッシュマシーンとして2558を買っていくのは楽しい作業となってくれそうです。
またブログでどれくらい買って、配当がどんな感じで育っているかは記事にしていこうと思います。
もしかするとドル建ての海外ETFよりも2558の方が使いやすい読者様も多いかも知れませんね。(全世界株式の2559という選択肢もありです)
ぜひ管理人と一緒にコツコツ配当を育てていきましょう。
お読み頂きありがとうございました。
応援クリックをして頂けると毎日更新する励みになります。
にほんブログ村
不労所得を増配パワーで何もせず増やしてくれ~という読者様からの応援ポチをお待ちしております。
関連記事です。
グッバイVT?東証で全世界株式ETF(信託報酬0.0858%)爆誕
全世界株式の2559ですね。こちらも二重課税調整がされており2558同様に超おすすめのETFです。
面倒な場合は2559と元気のポートフォリオが悩まず最強かも。
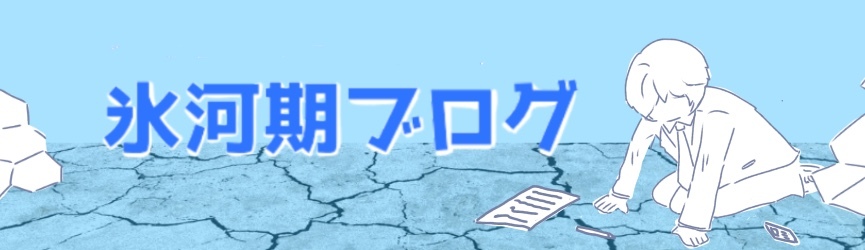

意外と読まれている記事