最近、シミュレーションの記事ばっかりだったので王道のお話。信託報酬は安いほど良いのですが、分かりやすい画像がXであったのでシェアします。
tweetはこちら。
楽天証券専売の激安ファンド、楽天・プラスの最新運用報告書が(9月下旬に)出たので、まず「S&P500」をまとめ。eMAXIS Slim、野村はじめてのNISAと比べても最安。総経費率でも、総経費に売買手数料や税金も加えた明細でも最安。(だからといってeMAXIS Slimの人が乗り換える必要はないよん) pic.twitter.com/4VpbIGL0Pt
— 綾小路麗香/マネー編集者 (@reika_amoney) October 27, 2025
そういえば総経費率とかすっかり誰も言わなくなった気がしますね。
では、画像などを見ながら再度勉強していきましょう。
【コスト大切】久しぶりに信託報酬を意識してみる
まずは画像から。
楽天S&Pの総経費率など。

信託報酬は0.077%なんですが、これは表向きの数字。
実質コストは0.089%かかっており、監査費用、保管費用、その他費用がかかるため、総コストは少しだけ上がります。
昔はそこそこ高いので隠れコストと言われていましたが、昨今ではこちらも激低になったので、あまり意識されることも無くなってきたのかも知れませんね。
参考までに楽天オルカンも。

こちらは本家オルカンに対抗するために出した商品。
とはいえ、その他経費がそこそこ高い感じ。
実質コストは0.118%となっています。
信託報酬単体だと楽天オルカンのほうが安いのに。。まぁ、ここらへんは流動性高い米国大企業だけで運用したらいいS&P500と新興国株とか含んでいる全世界株式の差かも。
昔は新興国株式の信託報酬とか高かったんよなぁ、とか。
さて、これだけだと短すぎるので、実質コストのことをChat GPTに教えて貰って少し勉強しておきましょう。
「信託報酬における実質コスト」とは、投資信託を保有する際に実際に投資家が負担している総コストを表す指標で、表面的な信託報酬だけではわからない“見えない費用”まで含めた実質的な負担額のことです。
◆ 信託報酬と実質コストの違い
● 信託報酬(表面上のコスト)
-
投資信託の運用会社・販売会社・信託銀行へ支払う管理費用
-
目論見書や運用報告書に年率◯%で記載される
-
基準価額に日々反映され、自動的に差し引かれる
しかし、投資信託の運用には信託報酬以外にもさまざまな費用が発生します。
◆ 「実質コスト」とは
以下を年間トータルで合計したものを指します。
実質コスト = 信託報酬 + その他費用(隠れコスト)
● その他費用の例
-
売買委託手数料
→ ファンドが株式・債券を売買する際のコスト -
監査報酬
→ 会計監査人に支払う費用 -
保管費用
→ 証券の保管に関する費用 -
その他費用
→ 有価証券取引税、為替関連コストなど
これらは日々控除され、運用報告書(交付運用報告書)にはじめて年間トータル値として開示されるため、購入前には完全にはわからない点が特徴です。
◆ なぜ「実質コスト」が重要なのか?
-
投資信託の実際の運用成績はコストによって大きく左右される
-
特に、
-
アクティブファンド
-
新興国債券・株式ファンド
-
ファンドラップやバランスファンド
などは「その他費用」が大きく、
信託報酬より実質コストが高いケースがある
-
→ 低コスト指数ファンドでも、実質コスト0.1% vs 信託報酬0.05%のように差が出る。
◆ どこで確認できる?
-
購入後:交付運用報告書の「費用明細」欄に記載される
-
購入前:過去の同ファンドの運用報告書(またはブログ等の紹介)が参考になる
ブログだと友人のなまずんがたまに実質コスト含めた比較記事を書いています。
【2025年5月】全世界株式インデックスファンドのリターン比較とおすすめ【リターン・信託報酬・実質コスト・純資産総額の一覧】
【2025年5月】米国株式インデックスファンドのリターン比較とおすすめ【リターン・信託報酬・実質コスト・純資産総額の一覧】
5月時点の記事ですが、インデックスファンドは半年程度でそんなに大きく改善できる商品も少ないでしょうし、自分が持ってる投資信託は他社比較でどれくらい?という感じで読んでみると良いかも。
あと、NISAでオルカンが有名になったからか、たまに日経などでも紹介されている様子。

出典:全世界株投資信託のコスト比較 2位はオルカン、1位は?
ちょっと画像の解像度が悪くて見にくくてスミマセン。
野村オルカン、純正オルカン、楽天オルカン、Tracerオルカンと上位4つは信託報酬も互角ですが、実質コストでは微妙な差が出ていますね。
十分な低コストなので気にする必要はないレベルですが、実質コストが安いほど、個人投資家が得られる利益は増えます。あと超長期なら複利で効いてくるのも大きい。しかもマイナスで効きます。

まぁ、一番人気の王道商品を選んでいるならそんな心配になる必要はありませんが。
◆ 実質コストの計算例
たとえば、
-
信託報酬:0.3%
-
その他費用:0.15%
であれば、
実質コスト=0.45%
実際にはこの実質コストのぶんだけ、基準価額が目に見えない形で下がります。
◆ まとめ
-
信託報酬は表面的なコスト、実質コストは実際の総コスト
-
実質コスト=信託報酬+その他費用
-
実質コストは運用報告書で年1回だけわかる
-
コストは長期投資のパフォーマンスに大きく影響するため、実質コストを意識することが重要
というワケで今日は久しぶりに信託報酬のお話でした。
私たち個人投資家はインデックス投資でリターンのコントロールはできません。しかし、低コストの商品を選ぶことで、支払う手数料を下げる=リターンを改善することはできます。
低コストの商品を選ぶのは個人投資家が使える数少ないフリーランチ。
しっかり実質コストの安い投資信託を選びつつ、コツコツ投資を続けていきましょうね。
お読み頂きありがとうございました。
応援クリックをして頂けると毎日更新する励みになります。
にほんブログ村
何やかんやで純オルカン選んでおくのが安心よなぁ、という読者様からの応援ポチをお待ちしております。管理人は取り崩し終盤の50年後に安心できそうな純オルカンをNISAで選びました。
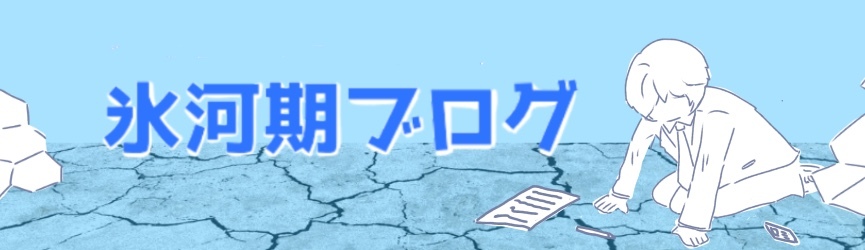

意外と読まれている記事