久しぶりに米ゼロクーポン債を見たら含み損がとんでもないことに。。
これならニッセイ4資産均等型を買って放置しておけば良かったなぁ、と後悔の日記ですw
記事終わりではゼロクーポン債とニッセイ4資産均等型の比較もしています。
もし良かったらお付き合いください。
【失敗談】ゼロクーポン債でなくニッセイ4資産均等型で良かったかも
まずはゼロクーポン債の含み損を見てみましょう。

スプレッド加味して100万円ちょい購入したところ、2025年5月13日時点で▲10.15%という惨状。
4月の急落を含め一番マイナスが大きかったのがゼロクーポン債という有様。
購入時が1ドル156円あたりだったことも大きいです。現在が148円あたりなので、これだけで損失率5%くらいあります。
買ったときはもっと本格的に円安がきたら怖いなぁ、と思っていたので円安ヘッジ的な考えでしたが、ハイパー高値掴み状態。
さて、これどうしたもんかな。。
満期まで保有すれば2倍くらいになるので為替損は気にならないレベルになりますが、表示画面にマイナスがあるのは精神的に良くない。
あと、4%くらいの確定利回りを取るならニッセイ4資産均等型を15年保有でも良かったんじゃないかな、と今さらになって思うことに。
まぁ、人間こういった身銭を切った失敗をして成長していくもの。管理人はとくにアホなので良い券になったと割り切るしか無さそう。
満期まで保有しようか悩んでいます。来年あたりに損出しして配当益と相殺でも良いんですけどね。
あとは満期時の円安ヘッジとして放置していても良いけど。(円高のときは個人向け国債が輝いているでしょう。)
関連記事ニッセイ4資産均等型のリーマンショック時の暴落耐性を調べてみた
今回の学び。
- たぶん、逆の動きで浮かれていても利益10万円だとそんな嬉しさはなくて、今のマイナス10万円の損失はプロスペクト理論で2倍ダメージだけを受けている
- たぶん、自分は株式の未来は信じられるけど、都度値動きのある為替商品(FX)や外国債券などはあまり好きではないようだ(最近買ったS&P500やNASDAQ100での損失は気にならない)
- 欲張ってガチャガチャするよりオルカンかS&P500と無リスク資産でバランスを取っているのが頭も使わず良い
3段論法で書くと自分のことが分かって良いですねw
読者の皆様におかれましてはクレバーに資産形成をおすすめします。
購入当初は16年後に2倍になること考えると為替変動あっても個人向け国債よりええかな、くらいの考えだったんですが、購入金額をもう少し低めにしておくべきでした。(遅すぎる反省。)
というワケで今日は短いですが、【失敗談】ゼロクーポン債でなくニッセイ4資産均等型で良かったかもというお話でした。
ちょっと短いのでAIにどっちがお得なん?と調べたものも応援クリックの下に載せています。AIが言うにはゼロクーポン債のほうがちょっと有利やで、となってるので、個人的には満期まで保有すればまぁそうだな、と思うもののスプレッドが大きいのも嫌だし、ゼロクーポン債を増やすのはここまでになると思います。
ところどころで失敗をしていますが、コツコツ積み上げてきた投資信託、海外ETFは十分過ぎるリターンを出してくれています。
まだまだ労働期間はあるので引き続きNISAを埋めながら資産形成をしていく予定なので今回の失敗も些細なことにしたいところ。
人間なのでいろいろ失敗しちゃいますが一緒に頑張っていきましょうね。
お読み頂きありがとうございました。
応援クリックをして頂けると毎日更新する励みになります。
にほんブログ村
156円での高値掴みm9(^Д^)プギャー、という読者様からの応援ポチをお待ちしております。マジで失敗が多いので反省です。
さて、AIに調べて貰ったニッセイ4資産均等型とゼロクーポン債の比較です。
2041年11月15日償還のゼロクーポン債は、現在から約16年6か月の保有期間があります。
このうえで、以下のように比較していきます。
比較視点:ニッセイ4資産均等型 vs 米ゼロクーポン債(2041年11月償還)
| 項目 | ニッセイ4資産均等型 | 米ゼロクーポン債(2041/11償還) |
|---|---|---|
| 投資対象 | 日本株・外国株・日本債券・外国債券(各25%) | 米国長期国債(利付無し) |
| 平均利回り(期待値) | 約3~4%程度(過去実績ベース) | 約4.2~4.7%(購入時イールド、為替除く) |
| リスク(年率) | 標準偏差8~9%(4資産分散により低め) | 米金利変動・為替リスクに大きく依存 |
| 為替リスク | 外国株25%、外国債25%(合計50%)分は為替影響あり | 全額ドル建て(為替変動の影響大) |
| 保有期間の制約 | いつでも売却可能(流動性高) | 満期まで約16年6か月必要 |
| キャッシュフロー | 分配金なし(複利運用) | 分配なし(満期までキャッシュフローなし) |
| 元本保証 | なし | 満期時ドル建てで元本+利息受取(為替で変動) |
観察ポイント
-
為替リスクはゼロクーポン債の方が圧倒的に高いです。償還時の円ドルレート次第でリターンは大きく変動します。
-
確定利回り(ドル建て)という点では、ゼロクーポン債が魅力的ですが、円建てで考えるとインフレや円高で実質リターンが目減りする可能性があります。
-
一方、ニッセイ4資産均等型は、過去20年のデータでは年率約3.3~4%程度に収まる「ミドルリスク・ミドルリターン」型ですが、リバランス効果で安定性は比較的高いです。
-
途中売却しない前提ならゼロクーポン債のリターンは悪くありませんが、ニッセイ4資産均等型も15年以上保有するなら、結果的にリターン差はそこまで大きくない可能性が高いです。
上記はスプレッドを考慮していないので、もう少し突っ込んだ内容を。
✅ 理論リターン vs 実務リターン(スプレッド・為替コスト込み)
| 比較項目 | ゼロクーポン債(楽天証券) | ニッセイ4資産均等型 |
|---|---|---|
| 理論利回り(ドル建て) | 約4.6~4.7%(満期まで保有時) | 約3.3~4.0%(過去20年平均) |
| 為替リスク | 全額あり(ドル建て) | 約50%が外国資産で為替影響あり |
| 途中売却 | 不利:債券市場+楽天証券の**スプレッド(1~2%)**が乗る | 基準価額で即売却可能(実質スプレッドなし) |
| 為替手数料 | ドル建て債券は片道25銭が一般的(楽天証券) | 外国資産部分はファンド内で処理される(手数料実質込み) |
| 分配金再投資 | 無し(複利) | 無し(複利) |
| 自由度・流動性 | 低い(途中売却にコスト・リスク) | 高い(いつでも売買可) |
| 税制 | 満期時 or 売却時に一括課税 | 基準価額に連動し譲渡所得として課税(20.315%) |
❗実際の売却時にはどうなるか?
たとえば:
-
理論価格が ¥12,482 でも、楽天証券での買取価格が ¥12,000 に設定されていれば、スプレッドで約¥482の損になります。
-
スプレッドは保有期間が短いほど影響が大きく、特に途中売却だと年率リターンが激減します。
✅ ニッセイ4資産の「手間のなさ」と「即時換金性」
-
ファンドは基準価額で換金でき、スプレッドも実質ゼロ。
-
購入・売却も楽天証券内で即日 or 翌営業日で完結。
-
為替も意識せずに、分散が効いたインデックス投資が続けられる。
✅ 総合評価(15年以上保有前提でも)
| 条件 | 有利な投資先 |
|---|---|
| ドル建てで確実に満期まで保有できる | ゼロクーポン債(高利回り・円安恩恵) |
| 途中で売る可能性がある/為替不安がある | ニッセイ4資産均等型が有利 |
| 換金性・柔軟性を優先 | ニッセイ4資産均等型 |
| 為替リスクを回避したい | ニッセイ4資産均等型(国内債券・株も含む) |
スプレッドを考慮するとニッセイ4資産均等型を買っとけとなりますね。円安対策を考えてもニッセイ4資産均等型なら半分は外国資産ですし。
満期保有したケースでも調べてみました。
これにより、両者の「実際の資産価値としての差」がより直感的に分かります。
📊 投資額10,000円に対する受取金額と年率リターン
| 投資先 | 受取金額(円) | 年率リターン |
|---|---|---|
| ニッセイ4資産均等型(年3.0%) | ¥16,286 | 3.00% |
| ニッセイ4資産均等型(年3.5%) | ¥17,641 | 3.50% |
| ニッセイ4資産均等型(年4.0%) | ¥19,101 | 4.00% |
| ニッセイ4資産均等型(年4.5%) | ¥20,674 | 4.50% |
| ゼロクーポン債(為替120円) | ¥16,086 | 2.92% |
| ゼロクーポン債(為替140円) | ¥18,767 | 3.89% |
| ゼロクーポン債(為替160円) | ¥21,448 | 4.73% |
✅ 分析まとめ
-
ゼロクーポン債は為替160円時に最大の受取額となり、ニッセイ年4.5%を超える
-
一方で為替120円だとニッセイ3.0%にも届かない
-
ニッセイの年率3.5~4.0%程度でも、為替140~150円なら拮抗してくる
為替と将来リターンのバランス次第で、どちらが有利かは大きく変わるということがはっきりします。
何度か再出力させたんですが、こうやって見ると分かりやすいですね。
結局は為替次第で、どっちもどっちという感じかも。
というワケでもし参考になった方がいらっしゃいましたら応援ポチを頂けると幸いです。
にほんブログ村
関連記事です。
ニッセイ4資産均等型のリーマンショック時の暴落耐性を調べてみた
暴落耐性だけでなく、けっこう過去のデータまで遡っています。AIに頼った部分が多いですが、参考になれば幸いです。
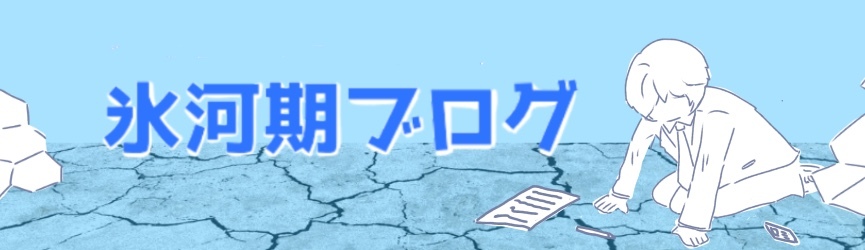

意外と読まれている記事